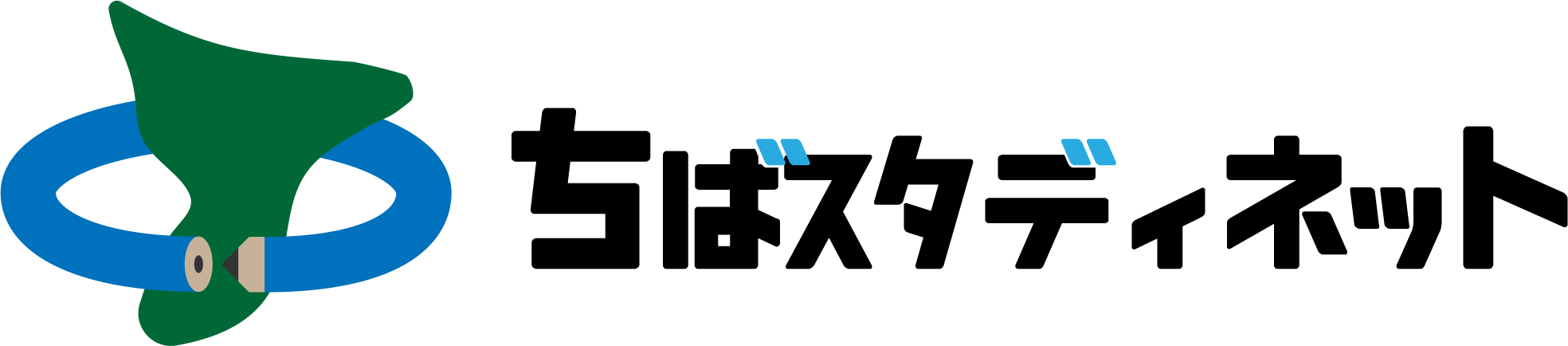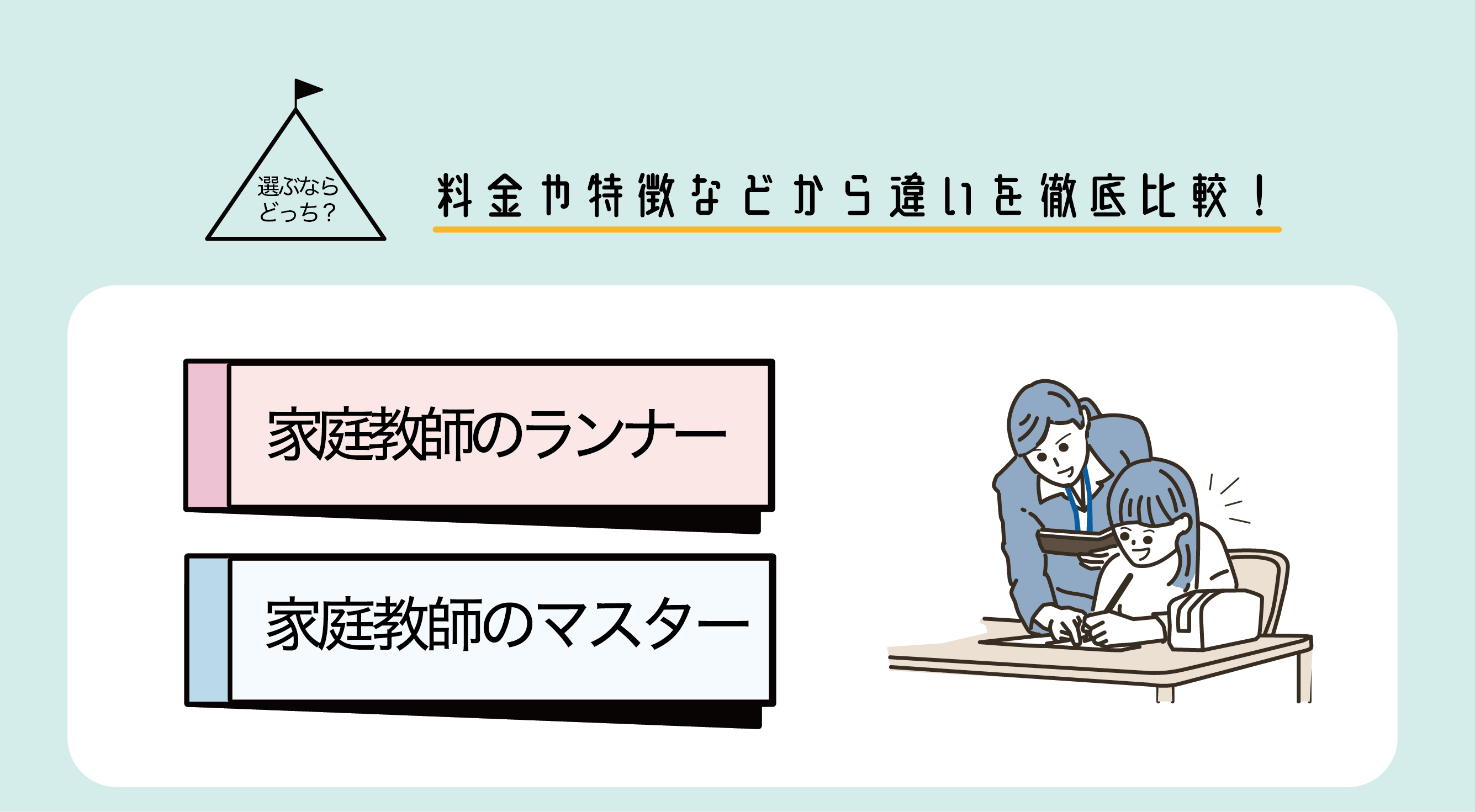『家庭教師のランナー』と『家庭教師のマスター』は何が違うの?料金や特徴など、具体的な違いを徹底比較!
このページでは『家庭教師のランナー』と『家庭教師のマスター』は、料金やホームページなどを見ると非常に似ていますが、実は全く別々の会社です。
このページではそんな2社の具体的な違いと「選ぶならどっちの会社か」を解説していきます。
『ランナー』と『マスター』の違いを一覧でチェック
| ランナー | マスター | |
|---|---|---|
| エリア | ほぼ全国 | 関東・関西 |
| 本部 | 東京都新宿区 | 東京都港区赤坂 |
| 指導料/1時間 | 1800円 ※高校生は2000円 |
小1~4…1600円 小5~6…1700円 中学生…1800円 高校生…2000円 |
| 交通費 | 上限なし | 上限なし |
| 管理費/月 | 小学生8,000円 中学生11,000円 高校生15,000円 (教材購入時は無料) |
学年により異なる※1 |
| 入会金 | 22,000円 | 22,000円 |
| 保証金 | 13,000円 | 不明 |
| 対象学年 | 小中高 | 小中高 |
| 主な指導内容 | 平均点以下 不登校 学習障害 塾で伸びない |
定期テスト対策 内申書対策 入試対策 推薦入試対策 |
| 教材 | あり・なし選択可 | あり・なし選択可 |
| 体験授業 | あり(無料) | あり(無料) |
| オンライン指導 | 対応 | 対応 |
※1…家庭教師のマスターでは指導料とは別に毎月「管理費」と「会費」が発生します。学年や申込コースにより金額が異なるため、詳しい金額はお問い合わせください。例1…中3生の場合17600円/月(会費+管理費) 例2…小5~6の場合13200円/月(会費+管理費) 例3…テキスト購入時は毎月管理費5500円(入会時中3または高校生の場合6600円)
表面上の違いはあまりない
ランナーとマスターはどちらの会社も「勉強が大っ嫌いな子専門」を大々的に掲げているため表面上はそこまで違いはありません。
また、料金に関しても若干の差はあるもののそこまで大きな違いはないように見受けられます。
細かいサービスに違いが!
ランナーとマスターとで、細かいサービスやサポート体制において違いがあります。
具体的な違いについてはこの後ご説明いたします。
『ランナー』と『マスター』の特徴とそれぞれの独自のサービスとは?
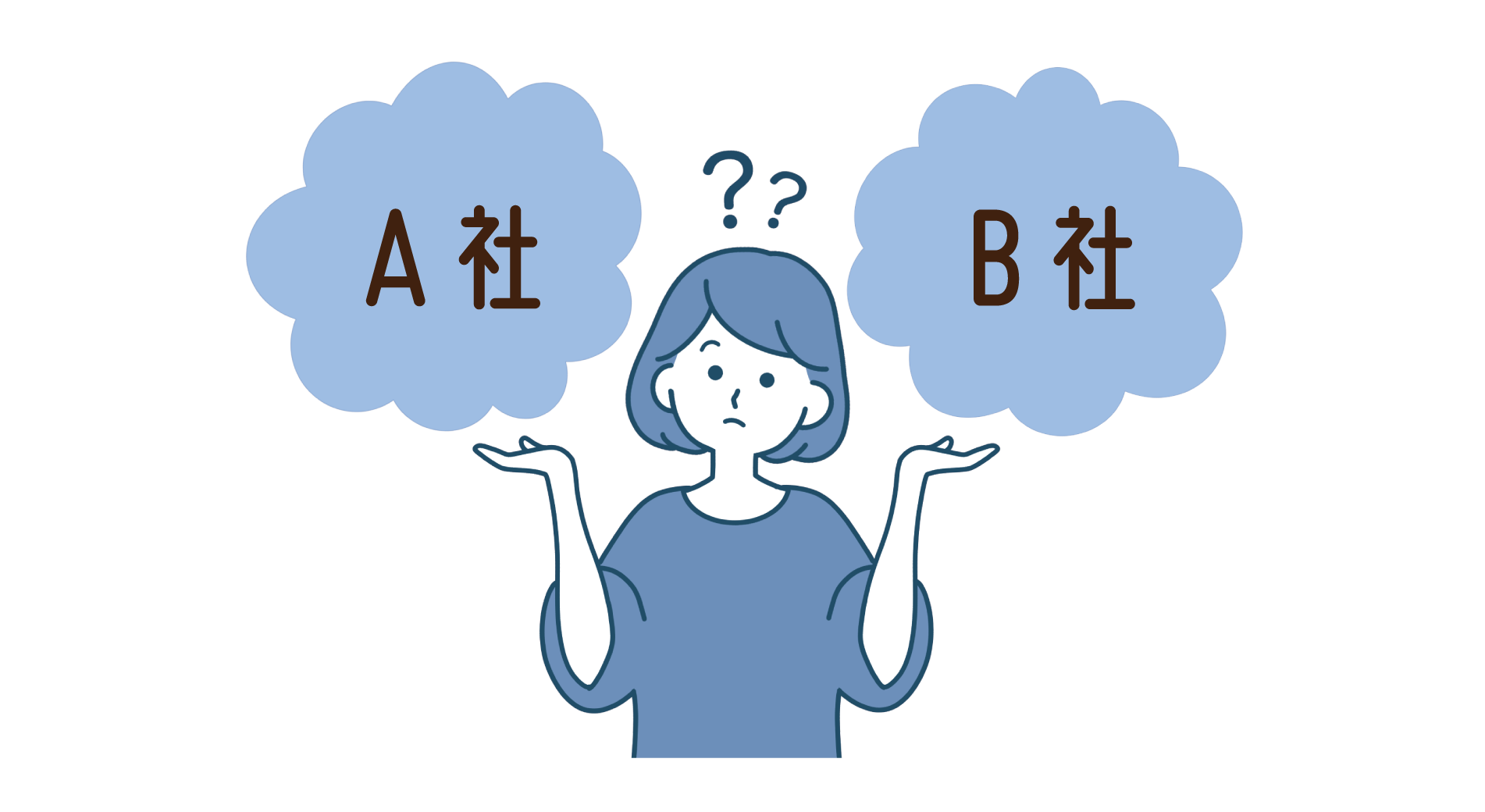
ランナーの特徴とサービスは?
『家庭教師のランナー』の特徴は勉強が大っ嫌いな子専門という点です。
勉強が嫌いでやり方がわからないお子さんに勉強のやり方から教えてくれます。
また、ランナーのサービスとして、無料の「LINE問題解説」というものがあります。
指導日以外にわからない問題が出てきて質問したいときに、ランナー本部の方へ質問すると解答解説が送られてきます。
ちなみにランナーには「エニスタ」という動画解説サービスもあります。
解答解説を読んだり、教科書を読んで理解したりするのが億劫な子には、非常に嬉しいサービスですね。
※中1~中3の学習内容の動画解説がいつでもどこでも見ることができます。(動画数221本)
また、ランナーの指導で使う教材はオリジナルの「スコアップ」というものを使うそうです。
マスターの特徴とサービスは?
『家庭教師のマスター』の特徴は勉強が大っ嫌いな子専門という点です。
そうなんです。実はランナーとマスターはコンセプトが同じなんですね。
ちなみにマスターでは、「TORE-CHA!」というポイント制度があります。
勉強を頑張った分だけポイントがたまり、素敵な景品と交換できるというシステムです。
これは、勉強のモチベーションを維持するうえでかなりメリットですね。
また、その他にも分からない問題をスタッフが電話やFAXで添削してくれるサービスもあります。
ちなみにマスターの指導ではオリジナルの「FOCUS」というオリジナル教材を使うそうです。
まとめると...
- ランナーは「LINEで質問」ができて「エニスタ(動画授業)」が見れる。
- マスターは「FAX・電話で質問」ができて、「ポイント制度(TORE-CHA!)」がある。
- 両社のテキストは異なる。
- コンセプトは両社ともに「勉強が大っ嫌いな子専門」
ということがわかりました!
『マスター』と『ランナー』の評判は?

『家庭教師のランナー』と『家庭教師のマスター』の口コミや評判はどうでしょうか?
主な口コミサイトやGoogleMapのレビューのリンクを掲載しましたので、そこから生の声をぜひご自身でご覧ください!
家庭教師ランナーの口コミ
家庭教師のマスターの口コミ
やるならどっちを選ぶべき?

【結論】大きな違いはない!
ここまで『家庭教師のランナー』及び『家庭教師のマスター』について調査してきましたが、コンセプトやサービス内容もかなり似ているため、どちらを選ぶとなると非常に難しいです。
なので、実際に資料を請求してみたり、体験授業を受けたりなどしてスタッフの対応や印象をみてみるのが重要です。
また、明確にちがうのは使用している「オリジナルテキスト」です。体験授業の際に実際のテキストの中身や使い方の説明を受け、自分に合っている方を選ぶのも有効です。